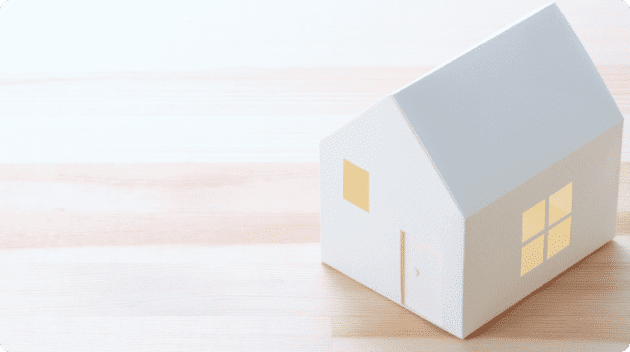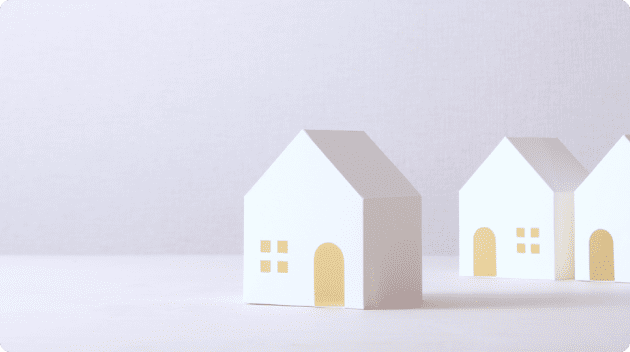接道2m未満の土地が建て替えできない理由は?有効活用する方法も紹介
接道2m未満の土地が建て替えできない理由は?有効活用する方法も紹介

土地の資産価値は大きく変動しにくく、既存の土地を利用して資産運用している方もいます。しかし、すべての土地で資産運用ができるとは限らず、なかには活用が難しい土地も多いです。活用が困難な代表的な土地は、接道2m未満の土地であり、この土地にある既存の建物は基本的に建て替えができません。
本記事では、接道2m未満の土地はなぜ建て替えができないのか、建て替えるためにはどうすればよいか解説します。建て替えが困難な場合の対処方法もまとめて取り上げるため、興味を持った方はぜひ最後までご覧ください。
接道2m未満の土地は建て替えられない3つの理由
接道2m未満の土地は、主に3つの理由で建て替えが実施できません。以下では、それぞれの理由について解説します。
建築基準法の条件を満たしていないから
建築基準法とは、建築物の敷地や構造、設備に関する最低限の基準をまとめたものです。1950年に制定され、建築物の安全の確保によって国民の命と健康、そして財産を守ることを目的としています。
移行、建築基準法は都度改正が加えられており、最近では耐震基準の見直しやアスベスト規制の強化などが行われました。
そして、建築基準法には接道義務に関する規定が含まれています。接道義務とは、読んで字のごとく敷地に建築物を建てる場合、建築基準法が定める道路に2m以上接していなければならないというルールです。
この条件を満たしていない土地に建造物がある場合は、増築や再建築は禁止、万が一工事中であっても作業を中断したり、工事途中の建造物を取り壊したりする必要があります。
安全確保のため間口は2m以上必要だから
間口とは、土地が道路に接している部分の長さのことで、道路に接している部分が長いほど間口が広いと表現します。建築物の正面・玄関側が必ずしも間口になるとは限らず、道路に接している面が長い方を間口と呼ぶケースが多いです。
道路から引きこみ部分があるような土地(旗竿地など)の場合は、一番狭い部分の両側に内接する円の直径を間口と考えます。素人では判断が難しいケースがほとんどのため、役所に聞いておきましょう。
建築基準法において、間口は2m以上なければなりません。これは、地震をはじめとする災害や緊急事態が発生した際、緊急車両が問題なく通行できる道を確保するためです。
緊急車両の幅は、消防ポンプ車が約2m、救急車が約1.9m、そして大型のはしご車が約2.5mです。間口が2mを下回ってしまうと緊急車両が通行できず、救助作業や消火対応が遅れてしまい、深刻な事態を招きかねません。
建築基準法が定める道路に面していないから
建築基準法における主な道路の種類は、以下のとおりです。
- 道路法による道路(第42条1項1号の道路)
- 開発道路(第42条1項2号の道路)
- 既存道路(第42条1項3号の道路)
- 計画道路(第42条1項4号の道路)
- 位置指定道路(第42条1項5号の道路)
- 2項道路(第42条2項の道路)
2項道路をはじめ、いくつか例外はありますが、建築基準法では原則幅員4m以上の道を道路とします。ただし、幅員が4mに満たない道路であっても、条件によっては建築基準法上の道路とみなされることがあります。上記の道路に接していない土地には、基本的に建築物を建てられません。
なお、自身が所有している土地と接している道路が建築基準法条の道路の定義を満たしているかは、役所の建築指導課で道路に関する図面を閲覧、取得することで調べられます。自治体によってはインターネットで確認できる場合もあるため、公式サイトをチェックしてみましょう。
接道2m未満の土地を建て替える方法は3つ
接道2m未満の土地にある建築物は、原則建て替えができません。しかし、まったく建て替えができないわけではなく、いくつか解決策も存在します。
接道2m未満の土地にある建築物を建て替える方法は、以下のとおりです。
隣の土地を一部購入する
接道2m未満の土地にある建築物を建て替える方法のひとつとして、隣の土地の購入が挙げられます。建築物の建て替えが禁止されているのは、接道義務を満たしていないためです。
つまり、土地を広げて接道義務を満たしてしまえば、建て替えはできるようになります。たとえば、現場接道幅が1.8mの場合、0.2m分の土地を購入すれば、接道義務を満たすことが可能です。
ただし、土地の購入をするときは、いくつか注意点が存在します。まず、購入を希望する土地の所有者とは、友好な関係を築いておきましょう。
土地は所有者にとって重要な資産であり、信頼関係が構築できていない相手に対して簡単に土地を渡そうとは思いません。土地の購入交渉で無理な要求や圧力をかけると、訴訟をはじめ深刻なトラブルに発展する可能性があります。
土地を購入するにあたって、費用相場も確認しておきましょう。土地の売買価格は、土地の持ち主や不動産会社が国土交通省や各都道府県などが算出する公示地価や基準地価などを参考に決めています。
土地の売買では、売主が価格設定の主導権を持つため、市場の動向によっては相場より高めに価格を設定することもあります。ただし、買主市場では価格交渉が厳しくなり、売主が必ずしも有利とは限りません。
そこで、事前に周辺エリアの地価を自分で調べておきましょう。地価は自分で周辺の物件の価格をリサーチしたり、公的価格を調べることでわかります。
また、信頼できる不動産会社に仲介を頼むのも有効な方法です。いずれにせよ、大きな買い物になる可能性が高いため、事前調査をはじめしっかりとした準備をしましょう。
隣の土地と保有している土地を等価交換する
隣の土地と保有している土地の等価交換するのも、接道2m未満の土地にある建築物を建て替える方法です。土地の等価交換とは、土地の所有者が土地の一部、またはすべてを手放す代わりに同じ価値の土地を取得することを指します。
売却と混同されやすいですが、売却は土地を手放すため土地とは縁が完全に切れるのに対して、等価交換は共有持分として一部は手元に残るため、土地と完全に縁が切れることはありません。等価交換は借入金や自己資金が必要ありません。そのため、開発後の建物の区分所有権や共有持分を取得できる点がメリットです。
一方で、土地の権利関係が複雑になる、交渉条件をまとめるのが困難などのデメリットもあります。とくに後者は、交換したい土地と自身が所有している土地の価値が釣り合っていない場合、等価交換そのものが成立しなくなる可能性も否定できません。
そのため、等価交換できるだけの価値がある土地を所有している場合に選択できる方法といえるでしょう。
なお、土地の等価交換をする際は、土地交換契約書を作成します。土地交換契約書に記載する内容は、交換物件の情報をはじめ、不可抗力による損失の負担や契約解除の条件などです。雛形がオンライン上で公開されているため、必要に応じて活用しましょう。
隣の土地を一部借りる
隣の土地を一部借りることで、接道2m未満の土地でも建築物の建て替えを実施できるようになります。土地の所有者にとって、土地の貸し出しは所有権を失わない、賃料が入ってくるなどメリットが多いです。そのため、土地の売買よりも交渉を進めやすいでしょう。
土地を借りる際の契約は普通借地、または定期借地の2種類です。普通借地は契約満了時に更新が可能な契約で、1回目は契約期間を20年以上、2回目は契約期間を10年以上に設定する必要があります。普通借地は、口約束でも契約が成立しますが、書面で契約するケースがほとんどです。
一方の定期借地は、期間が定められている借地権のことで、一定期間で必ず本来の土地の所有者に土地が変換されます。そのため、土地を貸す側にとって心理的なハードルが低いのが特徴です。また、定期借地権は必ず書面で契約を結ばなければなりません。
どちらの契約にもメリットとデメリットが存在するため、目的に合わせて選びましょう。たとえば、長期的に接道義務を満たしたい場合は普通借地がおすすめですが、建て替え工事を実施する期間のみ接道義務を満たしたい場合は、短期間土地を借りることで費用を抑えられる定期借地をおすすめします。
建築基準法上の道路に接していない土地を建て替え可能にする方法
接道義務を満たしているものの、土地に接している道路が建築基準法の道路でない場合も、既存の建築物の建て替えはできません。しかし、以下の方法であれば、建築基準法上の道路に接していない土地にある建築物の建て替えも可能になります。
43条但し書き申請をする
43条但し書き申請とは、再建築不可物件に対する救済措置のひとつです。この申請が認められると、接道義務を満たしていない建築物であっても建て替えが実施できるようになります。
43条但し書き申請を認めてもらうためには、道路や周囲の空地などの状況について一定の基準を満たし、かつ特定行政庁が安全上支障がないと判断してもらわなければなりません。なお、43条但し書き申請の手続きは、以下の流れで実施します。
- 事前相談、および協議
- 申請書類の作成と提出
- 本審査
申請の前に、まず特定行政庁と事前相談、および協議を行い、建築計画の内容の説明や必要書類について確認します。申請書類の用意ができたら、市町村の建築課をはじめとする担当課へ提出しますが、その際申請手数料が必要です。
申請手数料は自治体によって異なるため、事前に各自治体の公式サイトをチェックしておきましょう。最終的に建築審査会で行われる本審査で同意が得られれば、晴れて再建築の許可がでます。
なお、43条但し書き申請は永続性のあるものではないため、建て替えのたびに申請し直さなければならない点に注意してください。
位置指定道路の申請をする
位置指定道路とは、特定行政庁から「土地のこの部分が道路である」と指定を受けた幅員4m以上の私道のことです。位置指定道路として申請し、申請が認められれば私道が道路として扱われるようになるため、建て替えも問題なく実施できるようになります。
位置指定道路の申請は、指定を受けようとする道路が存在する自治体に対して行いますが、申請の手順は自治体によって詳細が異なる場合があるため、役所の建築課の担当者に詳しい手順を確認しておきましょう。
なお、位置指定道路は土地の一部を道路として指定しているため、固定資産税や都市計画税が発生するケースがある点に注意してください。また、土地の一部を道路として指定するため、その部分に建物は建てられないほか、申請にあたって土地所有者全員の同意も必要です。
セットバックを検討する
セットバックとは、土地と前面道路の境界線を土地側に後退させ、前面道路の幅を広げることです。
セットバックによって接道義務を満たせば、建て直しを問題なく実施できるようになります。道路の幅が広がり、見通しがよくなることで、防犯効果や交通事故の防止効果などが期待できる点もセットバックのメリットです。
一方で、セットバックを実施するためにはセットバックする分の測量や道路の舗装などを行う必要がありますが、それらにかかる費用を負担しなければならない点がデメリットとして挙げられます。セットバックする分の土地を公共の道路として提供する都合上、敷地面積は減ってしまう点にも注意が必要です。
セットバックで後悔しないためにも、費用はいくらかかるか、工事後どの程度の規模の建築物が建てられるかまで、あらかじめ把握しておきましょう。
接道2m未満で建て替えできない場合の活用法
最後に、建て替えがどうしてもできないときの土地の活用法について解説します。各方法の注意点について、順番にチェックしていきましょう。
リフォームして住み続ける
建て替えができないときの選択肢のひとつが、リフォームです。リフォーム内容によっては、建築確認申請が必要です。たとえば、増築や大規模の修繕を行う場合は、建築確認申請が必要になる場合があります。
リフォームの最大のメリットは、価格帯の安さです。建物の建て替えを行う場合、解体費用をはじめ、基礎工事費用や仮住まいの費用など、さまざまな費用がかかります。
一方、リフォームは全面リフォーム以外は工事する箇所をある程度限定できるため、余計なお金を消費する心配はありません。工事期間が短く、人件費が建て替えほどかからない点も安さにつながっています。
ただし、対象となる建築物の築年数によっては、工事費用が高くなる可能性がある点に注意してください。工事費用が高くなるパターンには、工事が始まってから追加費用が発生するパターンや、機材が搬入できず人件費が高騰し、全体の工事費用が高くなるパターンなどもあります。
また、住宅ローンが組めないケースもあります。住宅ローンは、リフォームをする際の費用としても活用できますが、再建築不可物件は流動性が低く、担保価値は高くないため、住宅ローンの審査を通過するのが難しい可能性が高いです。
賃貸物件にして貸し出す
建て替えができないときの解決策として、賃貸物件にして貸し出す方法も挙げられます。賃貸物件にして貸し出すメリットは多くありますが、そのなかでも大きいのはやはり家賃収入でしょう。
不動産の賃貸経営は、比較的安定収入を得やすいです。家賃収入を取得できるようになれば、維持管理費用や税金を捻出しやすくなります。賃貸経営の経験がなく、管理に自信がない場合は、管理会社に委託して代わりに経営してもらうことも可能です。
ただし、再建不可物件を賃貸として貸し出す場合はリフォームなどを行い、物件としての価値を高めてからの方がよいでしょう。リフォームをするためにはまとまったお金が必要になるため、どの程度費用をかけるかよく検討しなければなりません。
また、立地条件によって借り手が見つかる難易度は大きく異なります。たとえば、都心部へのアクセスがよく、商業施設が充実しているエリアは、幅広い層からの需要が期待できます。一方で、過疎化が進み、商店が少ないエリアでは、借り手が現れるまでに時間がかかることが多いです。
お金をかけてリフォームしても、借り手がいなければ賃貸にする意味はあまりありません。むしろお金をかけた分、赤字になってしまいます。賃貸経営をする場合は、再建築不可物件があるエリアの需要、家賃相場などを事前に調べておきましょう。
売却する
不動産を所有することにとくにこだわりがない場合は、売却もおすすめです。以下は、再建築不可物件を売却する場合の選択肢と、それぞれのメリット・デメリットになります。
隣地所有者に購入してもらう
選択肢のひとつが、隣地所有者への売却です。土地が広ければ間取りの自由度も高まり、財産価値も高まります。そのため、土地の所有者のなかには、土地の拡張を検討している方も少なくありません。
万が一売却が成立しなくても、土地の一部を買い取る、または貸し出すことで接道の問題を解決できる場合があります。少しでも可能性がある場合は、積極的に相談してみましょう。
ただし、隣地所有者の経済力に依存する方法のため、相手が土地を買い取るだけの資金力を有していない場合は諦めざるを得ません。また、経済力に問題がなくても、売り手に対して不信感を抱いている場合は土地を購入してもらえない可能性が高いです。
土地の売買をする際は、決して小さくない金額が動くため、互いの信頼関係が重要なポイントになります。普段から挨拶をする、相手が困っているときに積極的に手を貸すなどして、心象がよくなる行動を普段から心がけるようにしましょう。
建物を解体してから売却する
既存の建物を解体してから、土地だけ売却する方法もあります。建物付きの土地は用途が限定されてしまい、需要も高くありません。
しかし、土地だけなら用途が広がるため、需要が高くなる可能性があります。具体的には、周辺エリアに観光地や商業施設がある場合は駐車場として、近くに工場があれば資材置き場として活用することが可能です。
ただし、建物を解体する費用を出さなければならない点がデメリットとして挙げられます。解体にかかる費用は建物の大きさや使用されている建材によって異なるため、場合によっては高額な解体費用を用意しなければなりません。
たとえば、木造住宅の場合は1坪あたり2.5〜6万円が相場です。自治体によっては、家を解体するための補助金制度を設けている場合もあるため、必要に応じて活用しましょう。
ただし、建物を解体することで固定資産税や都市計画税の負担が増えるケースがあります。居住用の家屋などが建てられている土地には「一般住宅用地の特例」または「小規模住宅用地の特例」などが適応されることから、更地に比べて固定資産税・都市計画税が減税されているためです。
専門の不動産業者に売却する
再建築不可物件の売却をするにあたって、とくにおすすめの方法が専門の不動産業者への売却です。一般的な不動産業者では売却が困難、または安価でしか売却ができない土地であっても、専門の不動産業者であれば適切な値段で売却できる可能性があります。
また、現金化するスピードが早いため、新しく物件を購入する元手をすぐに入手できる点もメリットです。なお、専門の不動産業者を選ぶ際は、過去の実績や口コミを参考にするとよいでしょう。
まとめ
接道2m未満の土地にある既存の建物を建て替えられない理由や、建て替えられないときの解決策などについて取り上げました。接道2m未満の土地は、建築基準法を満たしていないため、接道義務を満たせるようにする、もしくは条件を満たして特例を適用してもらうなどしなければなりません。
ただし、いずれも手間と時間、そしてお金がかかるため、土地の売却も検討した方がよいでしょう。再建築不可物件の売却は、事故物件や特殊物件の買取を専門に行っているアウトレット不動産へご相談ください。
アウトレット不動産は、東京都をはじめとする関東地方を中心に土地の買取を実施しており、豊富な経験とノウハウを活かして売買の早期成立をサポートいたします。再建築不可物件の売却をご検討中の方は、ぜひ一度お問い合わせください。
CONTACT
アウトレット不動産への
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~18:00
(水曜・日曜・休日を除く) -
メールフォームでのお問い合わせ