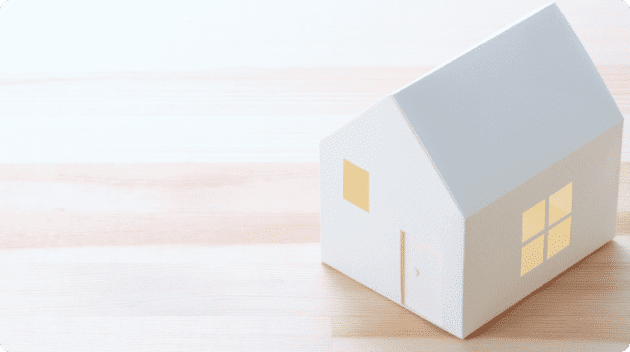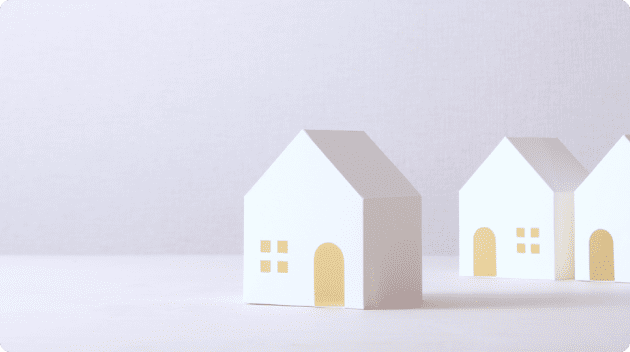東京、神奈川、千葉、埼玉の事故物件や特殊物件はアウトレット不動産にお任せください!
どんな訳あり物件・空き家も取り扱います!
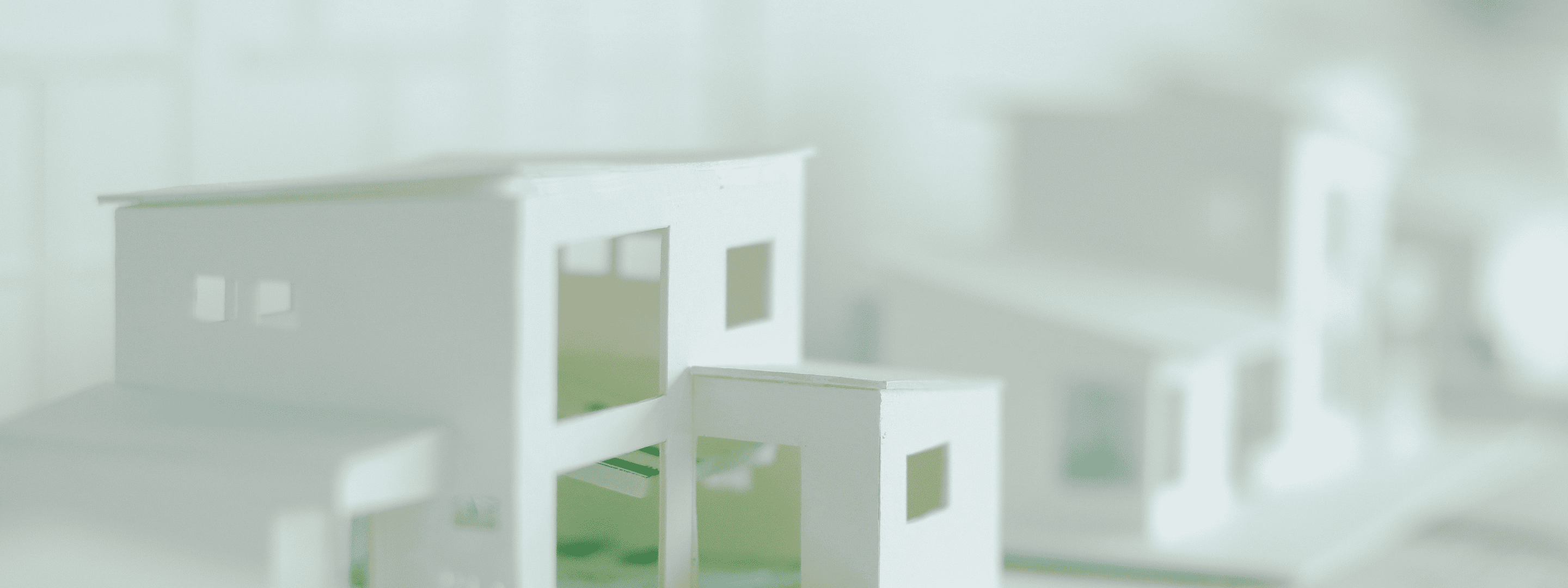
コラム
-

コラム
空き家の相続はどうするのが正解?活用法・売却法・節税術を解説
空き家を相続したものの、どう対応すればいいのかわからないとお悩みではないでしょうか。相続後の空き家を放置していると、固定資産税や維持費といった金銭的管理だけでなく、老朽化による近隣トラブルや資産価値の低下を招く可能性もあります。 本記事では、空き家の相続に関する基本的な知識から、具体的な活用法・売却手続き・節税対策まで実務的なポイントをわかりやすく解説します。空き家の現状と将来を見据えながら、適切な対応策を確認していきましょう。 空き家を相続するなら使い道を決めておこう丨放置するリスクとは 空き家を放置すると税金負担の増加や資産価値の低下、近隣トラブルの発生など、多方面に悪影響が及びます。こう […]
-

コラム
空き家の放置で固定資産税が6倍に?条件・対策方法・税の仕組みを解説
「親の住んでいた実家を相続したけれど、遠方に住んでいて管理が難しい」このような状況に直面する方は少なくありません。 しかし、空き家を放置すると、固定資産税の増加や建物の老朽化だけでなく、近隣住民とのトラブルや行政指導の対象になるリスクも発生します。 この記事では、空き家にかかる税金の基本、特定空き家や管理不全空き家に指定された場合の影響を詳しく解説します。空き家の活用・処分方法も紹介するため、ぜひ参考にしてください。 空き家にかかる税金丨固定資産税と都市計画税 空き家を所有すると、維持管理の手間だけでなく「固定資産税」と「都市計画税」の納付義務が発生します。これらの税金は空き家だけでなく、土地 […]
-

コラム
接道2m未満の土地が建て替えできない理由は?有効活用する方法も紹介
土地の資産価値は大きく変動しにくく、既存の土地を利用して資産運用している方もいます。しかし、すべての土地で資産運用ができるとは限らず、なかには活用が難しい土地も多いです。活用が困難な代表的な土地は、接道2m未満の土地であり、この土地にある既存の建物は基本的に建て替えができません。 本記事では、接道2m未満の土地はなぜ建て替えができないのか、建て替えるためにはどうすればよいか解説します。建て替えが困難な場合の対処方法もまとめて取り上げるため、興味を持った方はぜひ最後までご覧ください。 接道2m未満の土地は建て替えられない3つの理由 接道2m未満の土地は、主に3つの理由で建て替えが実施できません。 […]
-

コラム
どうすれば狭小地を買取ってもらえる?成功例や高値で売却するコツを紹介
狭小地の買取は、不動産買取業者や仲介サービスに依頼したり、隣地所有者に交渉したりする方法があります。しかし、一般的には狭小地の売却は難しく、放置するとさまざまなリスクがつきものです。 本記事では、狭小地を買取ってもらうのが難しい理由、放置するリスクをご紹介します。そのほか、高値で売却するコツや買取依頼の流れ、狭小地の活用方法もお伝えするので、狭小地の売却や再利用を検討している方はぜひ参考にしてください。 どうすれば狭小地を買取ってもらえる? 狭小地は、一般的な土地と比べると売却のハードルが高いといわれています。狭小地の売却を検討している方は、まずどのような方法で買取ってもらえるか確認しましょう […]
-

コラム
再建築不可物件はどうするのが正解?放置するリスクと一緒に解説
不動産には社会的な信頼が得られるほど資産価値があり、投資にも利用されています。しかし、不動産によっては売買が成立しにくいものもあります。購入者が現れなければ、その物件は資産どころか大きな負債になりかねません。 本記事では、売買が成立しにくい不動産の代表である、再建不可物件について解説します。 放置し続けるとどうなってしまうのか、また売却するためにはどうすればよいかまで取り上げるため、ぜひ最後までご覧ください。 再建築不可物件はどうする?建て替えが制限された要因 そもそも再建築不可物件とは、既存の物件を取り壊してしまうと、その土地に二度と物件を建設できなくなる物件のことです。不動産の購入希望者の […]
-

コラム
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは?責任を問われる事例や売主が注意すべき点も解説
売買した物件が契約内容と異なっていた場合、売主は買主に対してその責任を負わなければいけません。これを「契約不適合責任」と呼びますが、2020年4月1日以前は「瑕疵担保責任」という呼称でした。 「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更により、売主が物件の状態や契約内容に関して負う責任がより重くなっています。現在、住宅を売ろうとした場合、どんなことに気をつければよいのでしょうか。 この記事では「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違いを詳しく説明し、これから中古住宅を売却する際に注意すべきポイントを解説します。 瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは? 2020年4月1日の民法改正により、「 […]
-

コラム
事故物件で告知義務が発生する場合はどんなとき?告知すべき内容や注意点を紹介
事故物件とは「心理的瑕疵がある物件」のことを指します。多くの人は、人が亡くなった場合は事故物件だと思いがちですが、亡くなった理由によっては事故物件とはならないこともあります。 本記事では、事故物件の対象となる物件や告知すべき内容について紹介します。また、告知義務に違反した場合の影響や、注意すべき点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。 事故物件で告知義務となる対象は? 心理的瑕疵物件とは、過去に事件や事故があった場所、または特定の事情により居住者に不安や嫌悪感を抱かせる可能性のある物件を指します。事故物件には告知義務が発生し、売主や貸主はその事実を伝える必要があります。 人が亡くなる […]
-

コラム
心理的瑕疵物件とは?所有するリスクと売却する際の注意点も解説!
「心理的瑕疵物件」という言葉は、不動産取引の場で耳にすることの多い言葉です。これは、過去に事件や事故、あるいは周辺環境の問題などがあり、心理的な不安や嫌悪感を抱かせる要素を含む物件を指します。 物件の売却では、慎重な検討が必要とされるため、所有や売却のリスクを理解しておくことが重要です。 この記事では、心理的瑕疵物件の概要に加え、所有するリスクや売却時の注意点について詳しく解説します。 心理的瑕疵物件とは 心理的瑕疵物件とは、過去に事件や事故があった場所、または特定の事情により居住者に不安や嫌悪感を抱かせる可能性のある物件を指します。このような物件は、特別な配慮が必要なため、その特徴やリスクを […]
CONTACT
アウトレット不動産への
お問い合わせ
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~18:00
(水曜・日曜・休日を除く) -
メールフォームでのお問い合わせ